なにが発端だったのか? その経緯はよく覚えていない。
とにもかくにも北関東、茨城県の町まで遊びに出掛けることになった。
声を掛けてくれたのは、
私が住む那須のサ高住(サービス付き高齢者住宅)の元スタッフ。
そして、一緒にトールペイントサークルをやっている食堂スタッフ。
「ねえ、女棟梁さんチに行く話があるけど、行きたい?」と。
女棟梁、と言えば、わがサ高住の木の家々の建設にもかかわった人。
行きたい? と問われれば、そりゃあ、行きたい。
ぜったい、行きたい!
なにしろ、相手はあこがれの「女棟梁」なのだ。
そもそも、誘ってくれた元スタッフも元の仕事が、建築パースの制作。
彼女は、広い別荘地にログハウスを建てて、一人で住んでいる。
家のデッキも物置きも庭の東屋も、大きな木をチェーンソーで切り倒して、
自力でガンガン作ってしまうような人なのだ。
そうなのね、かの女棟梁とは「類は友を呼ぶ仲」なのね、と思いつつ、
弾む思いで私も車に乗り込み、一路、茨城の町へと向かっていった。
車で2時間ほどかかる。
とりあえず、昼食を済ませてから行こうね、ということになり、
途中、「チェルキオ」という、見た目うっとりの欧風レストランに立ち寄った。
そこは町が一望できる丘の上に立つ店で、店内は広く、たくさんの席があった。
けれど、けれど、シェフが一人だけ。ほかには、誰もいない。
で、使用するのはカウンターの5席のみということだった。
幸い席がちょうどあり、季節の素材を活かしたミラノランチなるものを頼んだ。
とても美味。「このシェフ、何者!」と、なにやら気分が急上昇したのだった。
ゆっくり食事を楽しんで、それからたどり着いたのは、
栗の林の中のなだらかな丘に、6軒の思い思いの木の家が点在する場所だった。
建築系の仕事をしていた女性たちが、協力し合って、それぞれにお気に入りの
家を建てたという。
棟梁の彼女の家は、ドアを開けて入ると、
中央にロフトに行く階段があり、ほかはドアが全くない。大きさの違ういろん
な窓からの風景にぐるりと取り囲まれたような開放的な家だった。
おお、と思った。
自分の家をどんなふうにでも自分で作ることができるなんて、
ああ、なんてなんて素敵なことなのだろう、と。
棟梁ならではの家づくりのその自由さに魅入られて、
なにかいきなり目が開かれてしまったような思いになった。
コーヒーを淹れてもらい、そのほろ苦い感じをしみじみ味わっていたら、
同じ丘に住む棟梁の友人がやって来た。
彼女に、初めましての挨拶をしたら、
「私たち、初めてじゃないわよ」と、にっこりされた。
女棟梁も「そう、昔、会ったわよ、私とも」と、だって。
そして、気が付いた。
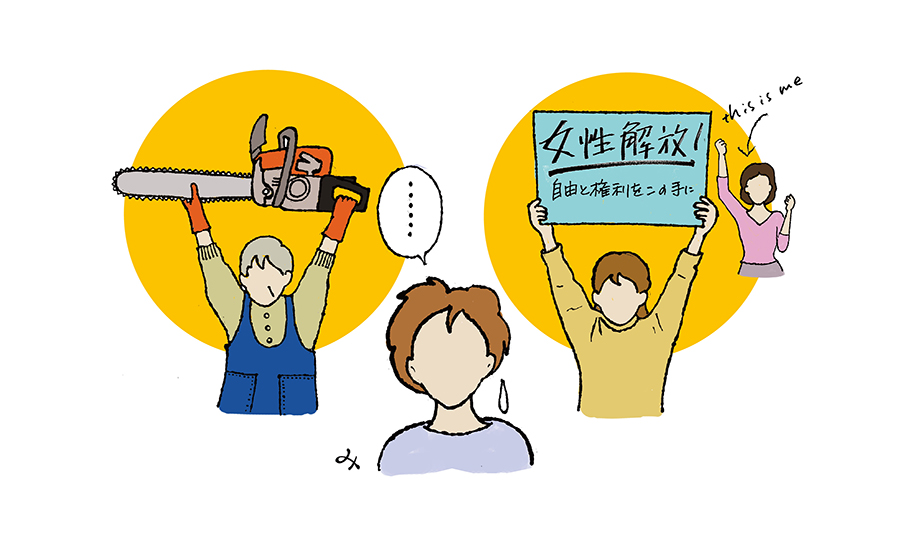
彼女たちとは、ウーマンリブ勃発の1970年代、共に街を徘徊していた同世
代だったのだ。頭がくらくらした。
あれから、なんと、なんと50年。人生、夢のごとし。
とうに半世紀もが、過ぎ去ってしまっていたのだった……。