人生は、時に思いがけない方向へと展開したりする。
それで、私は成りゆきまかせで生きればいいや、なんて思うようになった。
そんな私は、三十代の半ばに4歳の息子を連れてサーカスに入り、
一年ほどテントで暮らしたことがある。
なんでサーカスに? と聞かれるが、
その頃、SFの叙情詩人と呼ばれた作家、レイ・ブラッドベリの本に夢中だった。
頭の中がファンタジー状態だったのだ。
本に描かれる風をはらんだ天幕、玉乗りの少女、
色とりどりの衣装を着たクラウンたち……
シングルマザーの私は、保育園に行き渋る息子に手を焼き、
仕事にも嫌気がさしていた。
それで、そうだ、サーカスなら子連れでも働ける、と思った。
息子に「サーカスで暮らすってどう?」と聞くと、
「行く、行く」とぴょんぴょん跳ねて喜ぶので、
「幼いこの子の人生へのプレゼント」と思ったのだった。
サーカスで、私は炊事の下働き、息子は毎日、サーカスの舞台に夢中になって
過ごした。サーカスの暮らしは、子供にはファンタジー。
大人にはリアルで厳しい。
今思えば、頼らず、すがらず、自立して生きぬく修行のような日々だった。
なにしろ、1カ月に1回、自分のテントを壊して、別の場所にまた自分の寝小屋を建てる。
それが当たり前の日々だったのだ。
私はサーカスを出た後、取材を重ね、この体験をノンフィクションとして本にした。
ところがその本が、テレビでドラマ化された。
ドラマでは、不倫に敗れてサーカスに行った私は、なんとそこでサーカスの男と恋をする、
という筋立てになっていた。
そのぐらいにしないとドラマにはならないよ、というわけだった。
編集者やプロデューサーに「ケイちゃん、ここは、今後の生活のために」と説得され、
「まあ、いいか」とそれを了承した私だった。
だって、ビンボーだったから……。
でも、おかげで私は恥ずかしく、サーカスの人たちに合わせる顔もなく、疎遠になってしまっていた。
そのうちサーカスは倒産し解散してしまったのだった。
ところが、なんてことだろう!
那須に移住してきた私は、当時、サーカスで一緒だった美一さんに再会してしまった。
38年ぶりの遭遇だった!
彼女は、同じ那須町に暮らしていて、私が借りた「原っぱ」の地主さんと知り合いだったのだ。
その彼女が、最近ラインを立ちあげたので、
人から人へと鎖のようにあの時のサーカス村の住人たちがつながっていく。
北海道から、九州、四国……と、みな全国に散り散りになって、それぞれがそれぞれに生きている。
中にはまだ現役のパフォーマーもいる。
「原っぱ」でシニアたちのサーカスパフォーマンスが演じられるかもしれない。
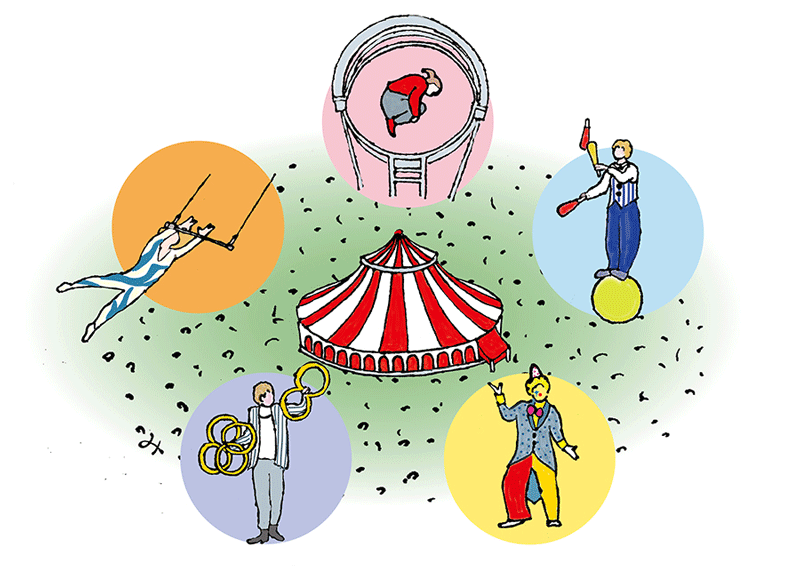
そんなことができたら……と夢見てしまう。
このコロナ禍である。
現実が厳しいとその分、頭の中のファンタジーがどんどん肥大化していく私である。

