お盆といえばお墓参り……世間一般ではそうなっている。
だけど、私の父は名古屋にある曹洞宗のお寺で生まれ育ち、
両親のお墓もそこにある。東京からはちょっと遠くて、なかなかお参りに行けない。
叔母夫婦がお寺の跡を継いで、お墓を守ってくれているので安心だけど、
そもそも父は、しきたりといったことに重きを置く人ではなかった。
こころで祈ればよい、こころで念じればいいんだよ、と言っていたし、
母に至ってはなおさら。
家に仏壇といったものはなく、
「だってあなた、実家がお寺よ」なんて言っていた母は、だからといって、
その大きな仏壇のような実家へお参りに行くことも、あまりなかった。
面倒くさいことはキライだったのだと思う。
そして父方の親戚も、「あの嫁は…」なんて咎めることもなかった。
考えてみれば、父も母も、それぞれ自由人だったと思う。
母の父親…かつての富士製鐵に勤めていた私の祖父は、
戦時中、軍部から無謀な鉄の増産を命じられ、
「たとえ天皇陛下の命令でも、化学の法則を変えるのは無理です」と断った、
と聞いている。
その結果、会社を辞めることになり、故郷の福島県に帰り、
私の記憶にある祖父は、小さな村の村長だった。
そんな父親のもとで育った母は、能楽や謡曲、お茶、短歌、文学に夢中で、
結婚しても、本を読みながら片足で赤ん坊をあやしているような人だった。
ふつうのお母さんとは、どこか違っていた。
ただ昔の人だけに、家事は完璧にこなし、家の中はいつもきれい、
料理上手でご飯もきちんと作っていた。
でも、家族みんなで夕ご飯を食べるとき、母はお稽古事でいないことが多かった。
それに対して父が文句をいうこともなく、
だから母はいつだって自分の好きなことに夢中だった。
大学を出て製鉄会社に勤め、祖父を通して母とお見合い結婚した父は、
曹洞宗のお寺の子として、日常のことをきちんと正しくやっていくのが
仏の道だと言っていた。
父は母には盲目的に従っていて、母が能舞台に立ったり、
母の短歌が歌集の巻頭に載っていたりすると、なんだかうれしそうだった。
そんな父を、母はちょっと鬱陶しがったりしていたけど、そんな父だったからこそ、
母は自分の好きなことに夢中になっていられたのだと思う。
私が20歳で家出したとき、父は「恵は修行に出たのだ」と言っていたそうで、
連れもどそうとはしなかった。
離婚して息子とサーカスに入ったときも、
孫を心配して様子を見にはきたけれど、やはり連れ戻そうとはしなかった。
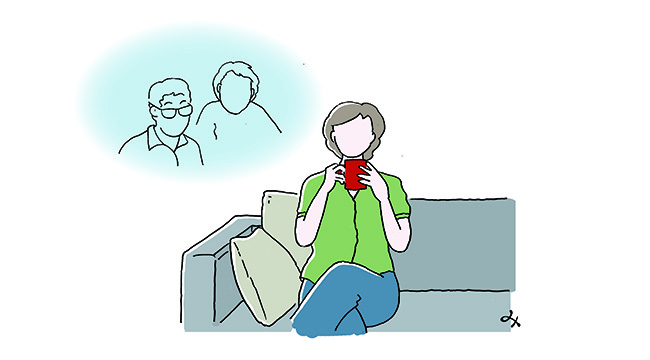
人は自由に生きればよい、と、父は考えていたのだろうか?
人は好きなことをして生きればよい、と、母は考えていたのだろうか?
お盆を前に、お墓参りに行かない娘は、こころで祈ればよいと言っていた
父と母のことを、あれやこれやと思い出している。